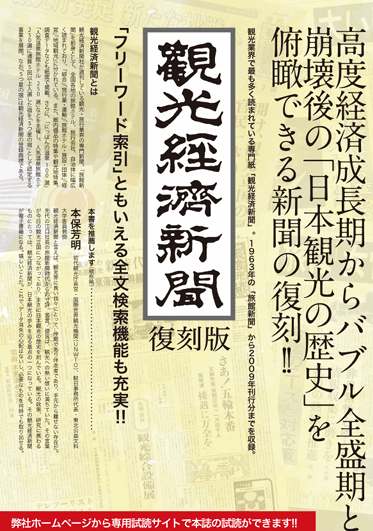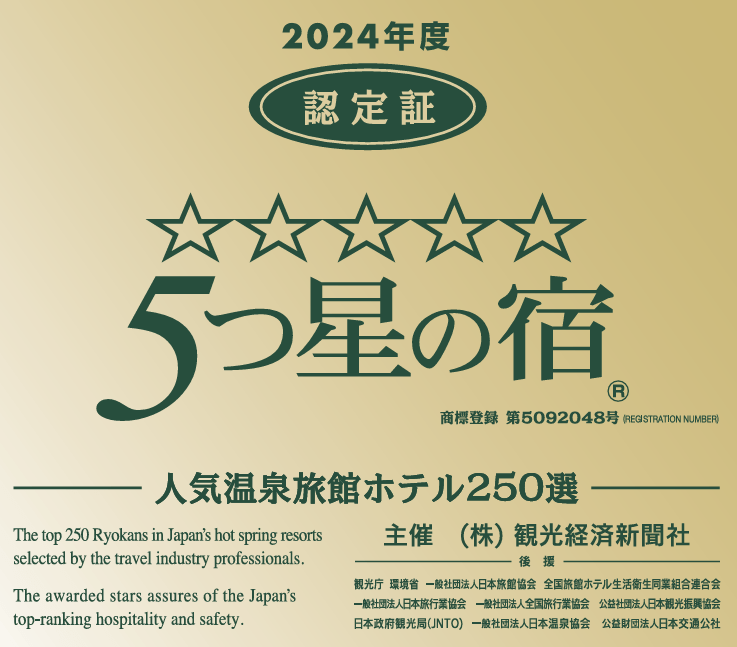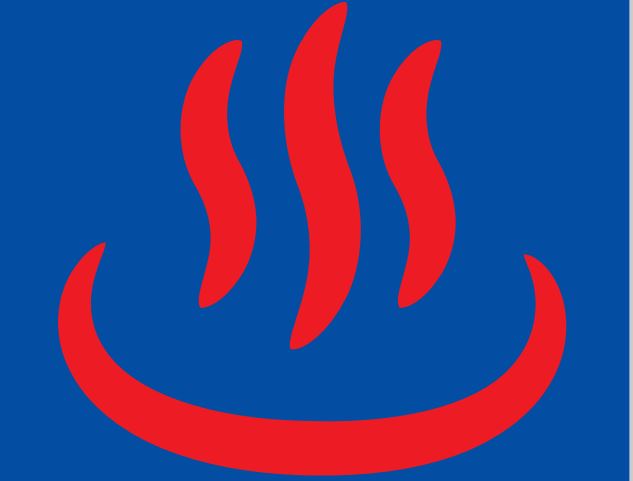1月1日付まで見てきたように、わが国における高速バスは、地方在住者の「都会への足」として成長してきた。地方部における乗り合いバス事業者は「地元の名士企業」であり、そのフラッグシップ商品として地元での認知が自ずと高まったからである。
一方、大都市部では、複数の乗り合いバス事業者が方面別に高速バスを運行することになり、乗り場や予約方法もバラバラで使い勝手が悪かった。また、彼らのほとんどは大手私鉄系のバス事業者であり、確かにその事業規模は共同運行先(地方の乗り合いバス事業者)に比べ何倍も大きいものの、その存在感は親会社の鉄道沿線という「線」に限られていた。
鉄道駅や車内掲出のポスターや沿線情報誌で高速バスの告知を行っても、首都圏、関西圏という「面」での認知拡大は進まなかったのだ。とはいえ、大都市側事業者が高速バスの成長に果たした役割は小さくない。
そもそも「共同運行制」それ自体を、業界内の利害調整を主導するとともに運輸省(当時)と掛け合って「勝ち取った」のは、京王、阪急、西鉄といった大都市側事業者である。
また、彼らが鉄道用地(高架下など)を活用するなどして都心の鉄道駅至近に大規模なバスターミナルを整備したことで、大量の高速バスを発着させることができるようになった。今日のウェブ予約につながる座席管理システムなどへの投資も、多数の路線を持つ大都市側事業者が主導したからこそ、実現したと言える。
彼らは、新宿や梅田、福岡などを拠点に、周辺県の事業者とそれぞれ共同運行で高速バスを運行したから、路線の「ハブ」に位置する事業者として営業施策や現場のオペレーション策定、それを支えるシステム開発などでリーダーシップを発揮した。
だが、市場(顧客)を握っているのは地方側事業者なのに、共同運行においてリーダーとして振る舞うのは大都市側事業という矛盾が、今思えば、1990年代後半以降の高速バスの成長鈍化と、競合する新たなビジネスモデルの登場を招いたという気もする。
(高速バスマーケティング研究所代表)